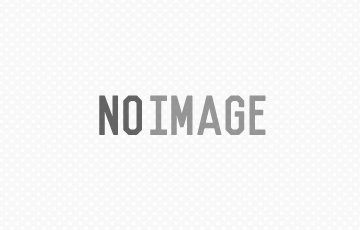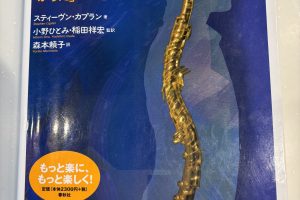こんにちは、ひろみです。
(写真は藝大在学時代の選抜オーケストラ公演 1st.Obは私です!懐かしいものが出てきたので)
前回記事の続きの響かせるについてです。
キャシー先生の「やろうとしてることが良い方向のことであっても、それをさせてくれないコンディションだったらそれは実現できない」が本当にそうだなーと思った時間だったのでとても印象に残っています。皆さんはどうでしょう?
- こうしたいという方向性(やろうとしていること)はもっているのに(わかっているのに)できない
- できたりできなかったりすることがある
- 練習ではできるけど合奏や本番ではうまくいかない
- 今日は調子が良い・悪い
この手のことはよく感じることではないでしょうか?
私たちって毎日同じようで毎日状態は違います。環境によって自分の気持ちが変化するのと同じように、自分のコンディションも変化します。その変化に気づいている日もありますが、気づかずにやっていることもあるのかもしれません。そんなコンディションを無視して「できる、できない」「調子がいい、調子が悪い」そう決めてしまうのはなんだか勿体無い。そのコンディションが悪いことで「やろうとしていること」をできにくくしているとしたら!?コンディションって実は自分である程度コントロールできるものなのです、というのが今回のテーマ。
「コンディション」という言葉の中にはとても多くの内容を含むので、少し範囲を絞った話題にしたいと思います。今回の話題の中心は「演奏に役立つ動きってなんだろう?」(前回記事)「その動きをつくるためのことを自分ってやってるのかなぁ?」(自己観察)今回は「それがやりやすいコンディションは?」というこの部分。自分のコンディションを自分で作るためには、普段から自分の状態に寄り添っている必要があります(すごく大事!)自分の構造がどんなもので、どんな機能を持っていて(当たり前すぎて考えた事もないようなことかもしれませんが)それを楽器演奏に意識的に取り入れるとどうなる?に興味を持ったり演奏に役立つ方法を考えたりしながら体験していく。簡単に言ってしまえば、そんな練習を繰り返しながら自分の状態を自分で組み立てることができるようになるということかもしれません。だって、自分をコントロールできるのは間違いなく自分なんだから!
「響かせる」に戻りましょう!(やっと 笑)
具体的にはまず響く=揺らぎや振動 というところを基に、筋肉緊張を最小限に、呼吸がしやすく演奏しやすい姿勢や構え方について丁寧に。骨の構造、マッピング、頭の位置。よーく観察するともっと自然なところが見えてきます。良い状態って良い姿勢で演奏し続けることではなく、いつでも自然な場所に戻ってこられるという自由さがあるということなんじゃないかなと思うんです。
その状態のまま「演奏する」
演奏するという動作の中にこの「響かせる」を共存させたい。それを最大限可能にするためには、演奏する時の力の使いかたというところが深く関わってくる。今回は「高音が特に」と気になっているので、高音の時にどんな動きをしている?自然な状態に近いままでどこまで音が出せる?出せない?頑張る場所ってどこだろう?今自分が力んでいる場所は?それって高音の演奏に必要?思考と力みは切り離せるかも!?など1つ試し演奏、それに1つ加えてまた演奏、こんなことやってみましょうか?と提案し演奏、と積み重ね(この生徒さん、動きを繊細にキャッチしてどんどん動きが変わっていくのです!!)最後には「高音だから」という響きの違いがほぼ聴こえないくらいの響きが出せるように。
今までとは違う響きを目指すということは今までとは違う動きをすること
でもその「今までとは違う」はそんなに遠いことをやる訳ではなくて、時としては自分では「そうなっていたことに気がついていなかったこと」だったり「しているつもりがやっていなかった」だったり「もう少し多く・少なく」ということだったりすることって多くって。
コンディションを整える、というのは等身大の自分で「今目指したいこと」をやりやすくするという自分コントロール。ここにアプローチしているのがアレクサンダーテクニーク。いやはやわかりにくいですが(笑)わかるとなかなか面白く奥深いものなのです。その面白さを繊細に受け取ってくれて実践してくれて「音」という形にして見せてくれたこの生徒さんのレッスンのおかげで、私自身も多くの感覚が言語化できて生徒さんから学ぶことは本当に多いのです。感謝!!